車には2種類の減速方法があります。それは「フットブレーキ」と「エンジンブレーキ」です。
普段、私たちが意識して使うのはフットブレーキですが、実はエンジンブレーキも非常に重要で、状況によって使い分けることで、運転の安全性が大きく向上します。教習所でも習うほど、どちらのブレーキも車には欠かせない機能なんです。
そこで今回は、フットブレーキとエンジンブレーキの違い、エンジンブレーキの使い方について解説していきます!
「フットブレーキ」と「エンジンブレーキ」の違いは?
車には2種類の減速方法である「エンジンブレーキ」と「フットブレーキ」があると説明しましたが、どのように違うのでしょうか?
それぞれの特徴や使い方を詳しく解説します。
フットブレーキ
フットブレーキは、車を減速させるためのメインのブレーキです。一般的には、アクセルペダルの左側にあるペダルを足で踏み込むことで、ブレーキがかかります。
フットブレーキには、ディスクブレーキやドラムブレーキなどのタイプがありますが、現代のほとんどの車にはディスクブレーキが採用されています。
フットブレーキは、普段の運転や急停止が必要な場合に使います。
例えば、信号待ちや渋滞時の減速、前方車両との距離を調整する際に使用するほか、道路に障害物が現れた場合や急な交通の変化に対応するため、急に減速や停止をしなければならないシーンでは欠かせません。特に、緊急時の急ブレーキではフットブレーキが非常に重要で、車をすばやく止めることができるため、メインのブレーキとして使用します。
エンジンブレーキ
エンジンブレーキは、エンジンの回転を利用した減速方法です。
車はアクセルを踏むことで加速しますが、走行中にアクセルを離すとエンジンの回転数が落ちることで、エンジン内部で発生する抵抗が車の動きを減速させます。これがエンジンブレーキの基本的な仕組みです。
走行中にアクセルペダルを離すだけでも、エンジンブレーキはかかりますが、エンジンの回転数が高ければ高いほど効きは強まります。特に、シフトダウンをすることでエンジン回転数を意図的に高くし、さらに強いエンジンブレーキ効果を得ることができます。これによって、下り坂や急な減速が必要な場面で、ブレーキの負担を軽減することができます。
ただ、フットブレーキと違ってブレーキランプが点灯しないため、後続車に減速を知らせることができないため注意が必要です。
エンジンブレーキの使い方
ここまでエンジンブレーキの特徴について説明しました。
では、実際にどのように使えばよいのでしょうか? 次に、エンジンブレーキの具体的な使い方を見ていきましょう!
エンジンブレーキは、走行中にアクセルペダルから足を離すことによってかかります。
ただ、エンジンの回転数が高ければ、その効果も強くなります。そのため、ギアを下げることで、意図的にエンジンブレーキの効き具合を調整できるのです。
AT車とMT車によって使い方が異なるので、それぞれ見ていきましょう!
AT車

AT車でのエンジンブレーキの効かせ方は、シフトレバーを操作します。
車種によっても異なりますが、一般的には「2」や「S」、「L」などのギアがありますので、そちらにシフトレバーを動かします。
走行中にアクセルを離し、シフトレバーを「S」や「2」に動かすか、MTモード搭載車の場合は「-」の方に動かしてギアを1つ下げます。
そうすることでギアが変わり、回転数が上がるため、エンジンブレーキの効きが強まります。
ただ、その状態でしばらく走っていると、徐々に回転数が落ちてエンジンブレーキの効きが弱まることがあります。その場合は、さらに「B」や「L」に入れることで、より強いエンジンブレーキをかけることができます。
同様に、MTモードの場合もさらにギアを下げることで、エンジンブレーキの効きを強めることができますよ!
MT車

MT車のエンジンブレーキの効かせ方も、基本的な原理はAT車と同じで、ギアを下げることで効きが強まります。
そのため、走行しているギアから1つ下げると、より強いエンジンブレーキをかけることができます。
ただ、シフトダウンの仕方には少しテクニックが必要で、回転数をしっかりと合わせてあげる必要があります。
そのため、ギアを1つ下げる前にアクセルをあおって回転数を上げておき、その状態でクラッチをつなぐと、ショックなくスムーズにシフトダウンできます。
これは「ブリッピング」というテクニックで、シフトダウンをする際によく使われます。ブリッピングをすると、ミッションなどの負担を減らし、乗り心地も良くなるので、身につけておくと便利です。しかもかっこいい!(笑)
なぜエンジンブレーキは使ったほうがいいの?
エンジンブレーキはあくまで補助的な減速方法です。
基本的にはフットブレーキを使って減速しますが、フットブレーキばかりに頼ると、ブレーキが効かなくなる危険性があります。
では、具体的にどのようなリスクがあるのか、そしてエンジンブレーキを使用することでどんなメリットがあるのか、一緒に見ていきましょう!

フェード現象を防げる
フェード現象とは、一言でいうと、ブレーキの効きが悪くなる現象のことです。
長い下り坂などでブレーキを踏み続けると、ブレーキパッドの摩擦材が過熱し、ガスが発生します。
このガスがブレーキローターとの間に入り込み、摩擦力を低下させることで、ブレーキが効きにくくなってしまうのです。
ベーパーロック現象を防げる
ベーパーロック現象も、フェード現象と同じようにブレーキの効きが悪くなる現象です。
ただし、その違いは、ブレーキの使いすぎによって摩擦熱が発生し、ブレーキフルードが沸騰する点にあります。
沸騰したブレーキフルードに気泡が混じることで、油圧が伝わりにくくなり、結果としてブレーキが効かなくなってしまうのです。
燃費の向上
エンジンブレーキを使うことで燃費の向上につながります。
アクセルペダルから足を離すと、エンジンへの燃料供給が止まります。
その結果、エンジンは燃料を消費せずに車を減速させるため、無駄な燃料の消費を防ぐことができます。
このように、エンジンブレーキを適切に活用することで、燃費を節約することができるのです。
エンジンブレーキはどんな時に使うといいの?
エンジンブレーキは、適切な場面やタイミングで使用することが重要です。
具体的には、以下のような状況で活用するのが効果的です。
下り坂
下り坂ではエンジンブレーキを積極的に使用することが推奨されます。
特に、長い下り坂や急な下り坂では効果が大きいです。
フットブレーキだけでずっと減速し続けると、「フェード現象」や「ベーパーロック現象」などのリスクにつながります。
そのため、エンジンブレーキを適切に使うことで、緩やかに減速できるだけでなく、フットブレーキの多用も避けることができます。
高速道路
エンジンブレーキの使用は、高速道路でも有効です。
特に、料金所付近や渋滞時にエンジンブレーキを意識的に使うことで、ブレーキの負担を軽減し、スムーズに減速することができます。
さらに、あらかじめブレーキをかけるタイミングが分かっている場面では、エンジンブレーキを使って事前に減速しておくことで、車への負担を減らすことができます。
ただし、注意点としてエンジンブレーキはブレーキランプが点灯しないため、後続車に減速していることが伝わりにくいです。
そのため、追突のリスクを避けるためには、必要に応じて軽くフットブレーキを使ってブレーキランプを点灯させ、後続車に減速を知らせることが重要です。
信号付近
信号付近でのエンジンブレーキの活用もおすすめです。
例えば、前方の信号が赤に変わっているのが見えた場合、事前にエンジンブレーキで減速しておくことで、急ブレーキを避けながら滑らかな運転ができます。
また、交差点付近や信号付近は人や車が飛び出してくることがあるため、あらかじめエンジンブレーキで速度を落としておくのは、安全面でも効果的です。
エンジンブレーキは適切に使う!
エンジンブレーキのメリットや使い方を説明しました。
フットブレーキを多用すると事故の原因につながりやすいため、エンジンブレーキを併用するのが効果的です。
ただし、エンジンブレーキに頼りすぎると、かえって危険な場合もあります。
少しでも危険を感じたら、迷わずフットブレーキを使いましょう!
エンジンブレーキはあくまでも補助的な減速方法なのです!
また、エンジンブレーキの活用は事故や故障の防止だけでなく、コスト面でもメリットがあります。
上手に使えば燃費が良くなり、ブレーキパッドの消耗も抑えられるため、結果的にメンテナンスコストの削減にもつながります。
エンジンブレーキを正しく使って、安全なドライブをしましょう!
それでは良いカーライフを!
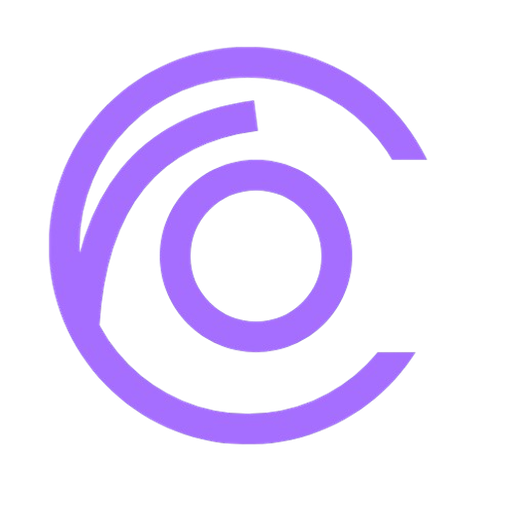
コメント